インターナショナルスクールに通う日本人の生徒は、どのような大学に進学しているのか?
■インターに通う日本人の生徒の進学先を大学の種類で分けると、下記の3タイプに分けられます。
①アメリカ、カナダ、イギリスなどの海外の大学に進学
②英語で行われる学部がある日本の大学に進学
③日本の大学の日本語で行われる学部に進学
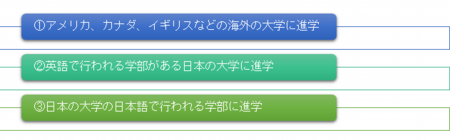
順番にみていきましょう。
①アメリカやイギリスなどの海外の大学に進学
インターナショナルスクール卒業後、最も多い進学先はアメリカの大学です。
現状としては、日本のインター卒の生徒のほとんどがアメリカやイギリスなどの海外の大学に進学するケースが多いです。
各インターナショナルスクールにもよるのですが、
ざっと20~30%の生徒が日本の大学に進学します。
60%~70%が北米の大学に、残りがヨーロッパ等の大学に進学します。
■その理由はふたつ
・英語が第一言語となる生徒が多いこと
・インターナショナルスクールのカリキュラムが日本の大学入試のシステムとは合わないこと
インターナショナルスクールでは主に英語で授業が行われるため、基本的には英語を話すようになります。
したがって、自然と進学先として英語圏の大学が選択肢に上がります。
学びたい事を学べる最適な場所として、世界中の大学が選択肢となりますので、日本以外の大学を検討することが自然となるのです。
またインターナショナルスクールのカリキュラムでは、日本の大学の一般入試に対応することが難しいという事実もあります。
しかし、日本の大学にも、AO入試や帰国子女枠等で、逆に英語を武器として受験することも可能です。
②日本で英語で行われる学部がある大学に進学(9月入学)
日本の大学を選択する場合、上智大学、国際基督教大学(ICU)、早稲田大学へ進学するインター生が多いのも特徴です。
上記の大学以外でも、インター生の受け入れ枠は広がっており、例えば東京大学では2012年度からすべての授業を英語で行うコース(PEAK)を開設しました。
2013年度の進学先が各インターのホームページで公表されていますが、印象としては、東京大学のPEAKに進学している生徒数が着実に増えています。
東京大学のPEAKを含め、このように近年、日本はグローバル化の重要性に気づき、異国の知識や文化を最大限に受け入れていく傾向を見せています。
(参考:グローバル30)
帰国生、インター生以外にも特に、より多くの外国人を入れるために、英語で行われるプログラムの実施が増加しています。
・東京大学PEAKプログラム
(http://peak.c.u-tokyo.ac.jp/index.html)
・早稲田大学国際教養学部、政治経済学部
(http://www.waseda.jp/sils/jp/)
・慶応義塾大学総合政策学部、環境情報学部
(http://www.sfc.keio.ac.jp/top.html)

東京大学PEAKプログラム 東京大学PEAKプログラムのホームページ
■理由として、日本の各大学が、世界で活躍できるような卒業生を輩出する重要さを認識していること。
世界中から生徒を集め、一人一人の生徒を広い視野で育成するという決断があります。
では、これらのこれらの英語プログラムの大学を卒業した日本人の学生はどのようところに就職しているのでしょうか?
ちょっと大きな枠ですが、日本の行政、経済界をはじめ、日本の外資系企業に就職、アメリカのキャリアフォーラムなどで職を探す等、海外での就職の選択があります。
海外で職を探す際も、大学・インターで築いた友人の輪を最大限に活用でき、仕事の場を世界へと広げている学生も多く見受けられます。
③4月入学で日本の大学の日本語で行われる学部に進学
その他の進学として、少数ですが、インターナショナルスクールを6月に卒業し、日本の大学に進学する生徒もいます。
いわゆる一般受験です。
一般受験を考えている生徒は、インター卒業後に予備校に通うなどして、日本の教育制度と同様に4月から大学に入学します。
この際、オプションがあるのが特徴です。
一般入試、AO入試、あるいは帰国入試という複数の経路での入学が可能です。
様々な大学がAO入学や帰国子女枠を導入しているので、選択肢が多いといえます。
それだけバイリンガルな生徒を受け入れたいという大学側の意思も働き、AO入学や帰国子女枠は、一般入試より、比較的入学しやすいのが現状です。
どの選択にせよ、インターナショナルスクールで培った『世界を広く見るという考え』は、グローバル化が進んで行く将来、さらに強みとなることがわかります。



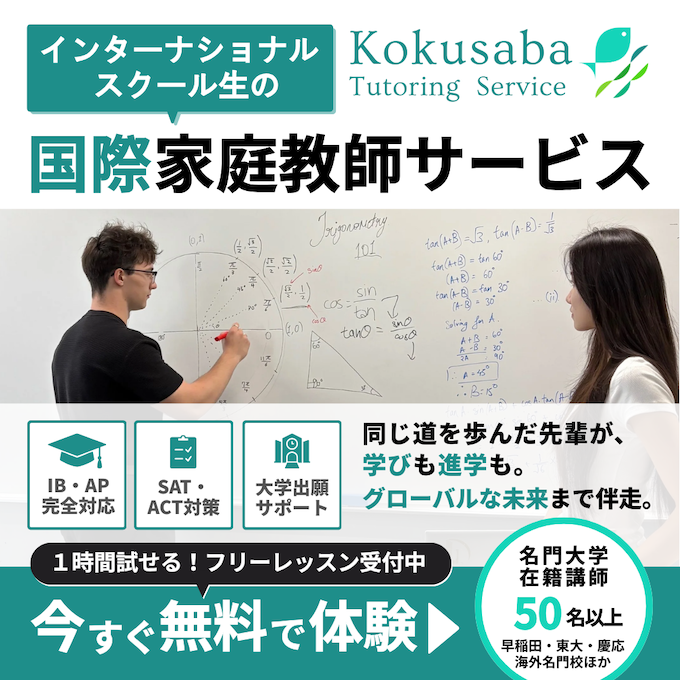


















インターナショナルスクールタイムズの編集長として、執筆しながら国際教育評論家として、NHK、日本経済新聞やフジテレビ ホンマでっかTV、東洋経済、プレジデント、日本テレビ、TOKYO FMなど各メディアにコメント及びインタビューが掲載されています。
プリスクールの元経営者であり、都内の幼小中の教育課程のあるインターナショナルスクールの共同オーナーの一人です。
国際バカロレア候補校のインターナショナルスクールの共同オーナーのため国際バカロレアの教員向けPYPの研修を修了しています。