世界第1位のMBA、スタンフォード大学経営大学院
英ファイナンシャル・タイムズ(FT)が毎年発表する「Global MBA Ranking 2019」で2年連続で世界1位に輝くスタンフォード大学経営学院(Stanford Graduate School of Business)。
数々のベンチャー起業家と輩出しているスタンフォード大学。
2018年1位、2019年1位と2年連続ファイナンシャル・タイムズ(FT)のMBAランキングで1位になっている。
2位は、ハーバード大学経営大学院、3位は、フランスにあるInsead。
Yahoo!やサンマイクロなどシリコンバレーのベンチャー企業を生み出してきたスタンフォード大学。
そのためスタンフォード大学の卒業式は、スピーカーも毎年注目を集める。
2005年の卒業式では、Apple社の故スティーブ・ジョブズ氏が卒業式のスピーチを務め「Stay hungry, stay foolish」で締めくくられたスピーチが伝説となった。
2019年の卒業式では、Apple社のティム・クックCEOがスピーチをし、歴史に残るスピーチとなりました。
▼ 故スティーブ・ジョブズ氏のスピーチがスタンフォード大学から公式に公開されている。
スタンフォード大学経営大学院のエグゼクティブコース
スタンフォード大学経営学院には、世界的な大企業の重役向けのエグゼクティブコースがあります。
それがAsian American Executive Programです。
世界的な大企業の重役向けのエグゼクティブコースは、経営大学院の奥の院とも言える。
先着50名の中高生!
今回、講師を務めるWesley J. Hom氏は、そのエグゼクティブコースの開発者。
Wesley J. Hom氏もIBM世界本社の副社長などを歴任してきたグローバル企業の経営者として活躍し、スタンフォード大学経営大学院のエグゼクティブコースを開発してきた。
そのHom氏の授業が武蔵野大学附属千代田高等学院で10月28日(月)に海外留学を希望する中学生、高校生(先着50名)向けに公開される。
「アジア人はどのように世界でリーダーシップを発揮できるか」をテーマに開催される公開授業に編集部も大注目。
日本ではソフトバンクグループの孫正義氏、ファーストリテイリングの柳井正氏、以降目立ったベンチャー起業家が出ていない。
その一方で、中国ではベンチャー企業が大きく育ち、アリババグループのジャックマー氏は、元英語教師だったこともあり、教育現場に戻りたいと引退し、教育への情熱を向ける。
日本の20年後を変えるのは、今の中高生。
だからこそ、「アジア人はどのように世界でリーダーシップを発揮できるか」のテーマに果敢に挑んで欲しい。
編集部は、本イベントを開催し、2020年4月に医学部・歯学部・獣医学部を目指すMIコース(メディカルインテリジェンス)も開講する話題の武蔵野大学千代田高等学院に注目。
世界1位のスタンフォード大学MBAスクール当日の授業を含め特別レポートします。
お問い合わせ
日時:2019年10月28日(月)17:00~19:00
定員:先着50名
会場:武蔵野大学附属千代田高等学院 新館1F 視聴覚室(
(東京都千代田区四番町11)
対象:中学生、高校生
会費:無料(交通費は参加者負担)
内容:第1部 公開授業「アジア人はどのように世界でリーダーシップを発揮できるか」講師 Wesley.Hom氏/第2部 海外留学経験者によるパネルディスカッション
申込方法:電話、FAX、メールまたはWebサイト申込みフォーム
電話:03-3263-6551
FAX:03‐3264‐4728
e-mail:nyushi@chiyoda.ed.jp
なぜ、武蔵野大学附属千代田高等学院が注目されるのか?
今回、スタンフォード大学ビジネススクールの創設者 Wesley Hom氏の公開講座を開く武蔵野大学附属千代田高等学院に編集部は、2014年から注目してきた。
首都東京の千代田区に国際バカロレア認定校がなかった中、武蔵野大学附属千代田高等学院は、千代田区初の国際バカロレア認定校になると共にIBコースを開講。
さらに文理探究のIQ、グローバル・アスリートのGA、リベラル・アーツのLA、メディカル・サイエンスのMS、医学部・歯学部・獣医学部を目指すMIコース(メディカルインテリジェンス)が2020年4月開講予定と6コースと多様な生徒の学びをサポートしている。
生徒の学びを6コースで応援する仕組みがある同校のチャレンジを今後も、レポートしていく。






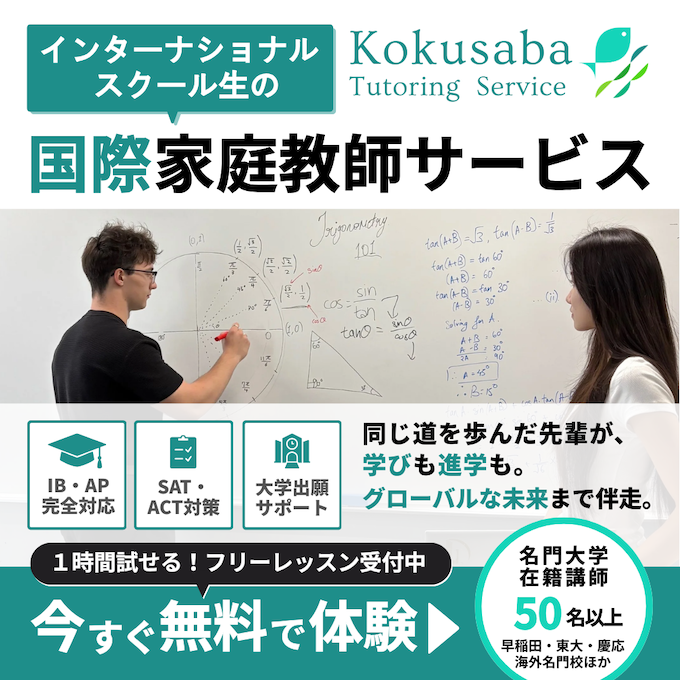



















インターナショナルスクールタイムズの編集長として、執筆しながら国際教育評論家として、NHK、日本経済新聞やフジテレビ ホンマでっかTV、東洋経済、プレジデント、日本テレビ、TOKYO FMなど各メディアにコメント及びインタビューが掲載されています。
プリスクールの元経営者であり、都内の幼小中の教育課程のあるインターナショナルスクールの共同オーナーの一人です。
国際バカロレア候補校のインターナショナルスクールの共同オーナーのため国際バカロレアの教員向けPYPの研修を修了しています。