多くのインターナショナルスクールは独立した運営です。
そのなかで、大学と提携および大学が運営をしているインターナショナルスクールが出てきました。
その代表が関西学院千里国際中等部・高等部と大阪インターナショナルスクールです。
1990年代に、大阪に帰国子女のための学校が必要だ、という意見とインターナショナルスクールも必要だ、という意見がありました。
実は、当時、大阪にはインターナショナルスクールがありませんでした。
そして、大阪になくても困らない理由がありました。
それは、距離的に近い神戸に複数のインターナショナルスクールがあったからです。
しかし、大阪にもインターナショナルスクールが必要という判断から、大阪インターナショナルスクールが創設されました。
2010年に関西学院と提携。
名前も「関西学院千里国際中等部・高等部」と変更し、大阪インターナショナルスクールも「関西学院大阪インターナショナルスクール」と名前を変更しました。
英語イマージョンプログラムをより進化させた「シェアードプログラム」を採用し、大阪インターナショナルスクールと一体化した運営がされています。
関西学院千里国際高等部と大阪インターナショナルスクールの卒業生は、関西学院に進学しています。
実は、ここがおもしろいのですが、帰国子女の教育学校とインターナショナルスクールの校舎をひとつにして、そのなかにふたつの学校組織を作りました。
そして、共同で授業を受けるようにしたり、学校行事などもひとつになって開催する新しい教育を構築しました。
その結果、千里国際の生徒は英語で学ぶ(イマージョンプログラム)から、さらに進化した「ともに授業や行事を分かち合う(シェアードプログラム)」という独自の教育を受けています。
この試みは、今後、ますます注目されてくると思います。

2011年には、同志社が同志社国際学院初等部・国際部を創立。
その証に、このシェアードプログラムを2011年に同志社が導入しました。
京都に同志社国際学院を創設し、一から学校を創るほどの力の入れようです。
同志社国際学院には、初等部(小学校)と国際部(インターナショナルスクール)があります。
ちなみに千里国際は、中等部、高等部があり、大阪インターは幼稚園から高校までのカリキュラムがあります。
同志社国際学院の初等部はその後、国際部(インター)に合流していきます。
インターの良いところと日本の学校の良いところをさらに引き出すのが「シェアードプログラム」といって良いかも知れません。
2011年には、同志社が同志社国際学院初等部・国際部を創立。
日本の小学校とインターナショナルスクールの一体運営を開始しました。
同志社国際学院は、初等部60人が中学校相当になると国際部(インターナショナルスクール)に合流します。
どちらも関西の有名私立大学の付属校です。
大学の教育学部附属のインターナショナルスクールの計画も。
教育学部附属でインターナショナルスクールの計画しているのが、千代田インターナショナルスクールです。
国際バカロレア教育を実施し、教員養成として教育学部の附属を計画しています。
教育学部附属のインターナショナルスクールとして、新たな動きといえます。
教育養成と国際バカロレア
国際バカロレアを教えられる教育養成が課題となっています。
千代田女学園と千代田インターナショナルスクールを運営する武蔵野大学は、教育学部の附属として千代田インターナショナルスクールを運営する計画です。
現在のところ国際バカロレアの教育養成は、東京学芸大学、玉川学園大学など教育養成を実施しています。
充実した教育養成の玉川大学
教育養成の代表の東京学芸大学
千代田インターナショナルスクールを併設する武蔵野大学教養学部の取り組みは、インターナショナルスクールと国際教育の教員養成として、注目を集めそうです。






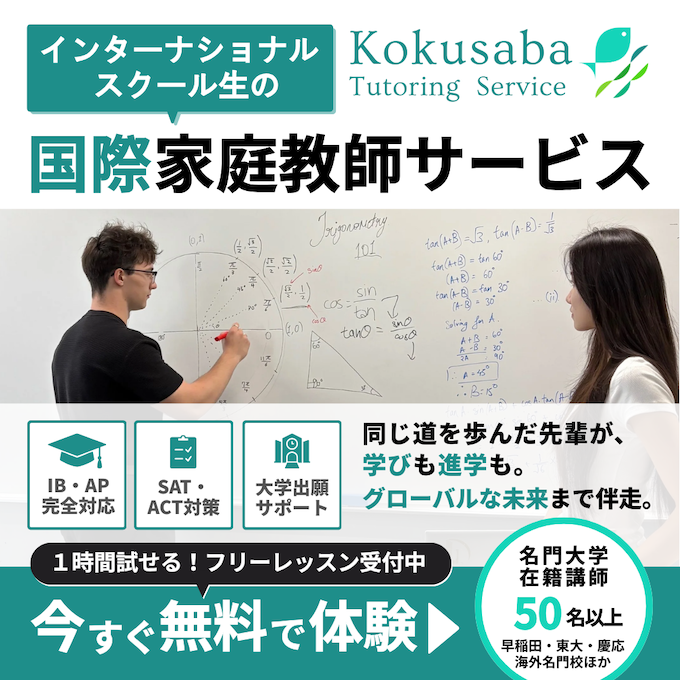

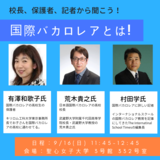




















インターナショナルスクールタイムズの編集長として、執筆しながら国際教育評論家として、NHK、日本経済新聞やフジテレビ ホンマでっかTV、東洋経済、プレジデント、日本テレビ、TOKYO FMなど各メディアにコメント及びインタビューが掲載されています。
プリスクールの元経営者であり、都内の幼小中の教育課程のあるインターナショナルスクールの共同オーナーの一人です。
国際バカロレア候補校のインターナショナルスクールの共同オーナーのため国際バカロレアの教員向けPYPの研修を修了しています。