現在、インターナショナルスクールについて書かれた本が多く出版されています。
現在、インターナショナルスクールについて書かれた本が多く出版されています。
では、どのように参考にしていけば良いのでしょうか?
参考にするにあたり、まず考えるべきは、著者の立場です。
著者の立場は、大きく3つに分類されます。
1、インターナショナルスクール関係者が書いた本
2、国際教育の専門家がインターナショナルスクールについて書いた本
3、教育関係者が国際バカロレアとインターナショナルスクールについて書いた本
それまであまり広報活動をする必要のなかったインターナショナルスクール。
そんなインターナショナルスクールにとって、取材を受けるメリットはあまりありませんでした。
そのため、マスコミが本格的な取材をし、書くことはかなり難しいことでした。
そのなかで最初に書くことができたのは、中の人でした。
すなわちインターナショナルスクール関係者です。
スクールについて熟知しており、情報量が多く詰まった本を出すことができました。
実は、編集部が一番最初に出会った本もスクール関係者の本でした。

2000年4月に第一版が出たセント・メリーズ・インターナショナルスクール 事務長をされていた白 雲龍(ハク ウンリュウ)さんの「自分をほめない日本人―日本の教室では学べない国際社会の対処法」です。
インターナショナルスクールでの50年にわたる経験から書き起こされた本書は、インターナショナルスクールのみならず、日本の教育についてユーモアを交えた考察で書かれています。
例えば日本の教育について次のように書かれています。
詰込み型教育について、こう述べた後次のような意見を述べています。
日本の学校教育は一般的に一方通行で、一人の教師が何人もの生徒を教えています。
これは情報を詰め込むにはふさわしいかもしれませんが、それを活用するという意味では、あまり感心出来ないと思います。
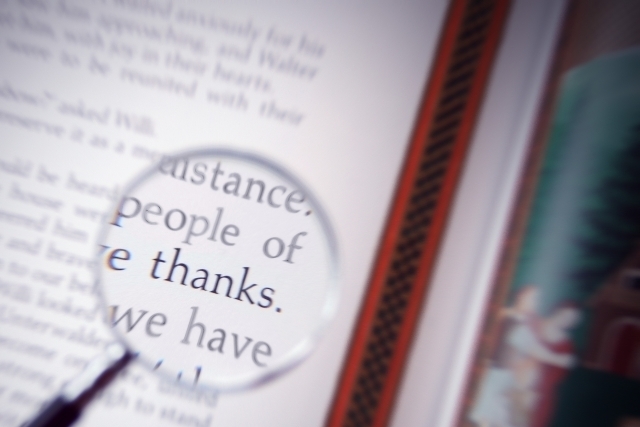
学校というところでは、何を教えているかではなく、生徒が何を学んでいるかということが大切なことだと思います(以下略)。
シンプルな分、重みがあります。
また、日本の英語教育についても車の運転をたとえて最後にこう書かれています。
*括弧内は、タイムズが足した部分です。
日本における英語教育は、英語を道具としてうまく安全に使いこなすことを教えるのではなく、英語という言語の構造を教えているのです。
(略)本当は車を運転する方法(英語をどう使うか)を学ぶことが必要なのに、構造ばかり(言語学としての英語)教えられているので、いつまでたっても運転はできません。
また、言語学としての英語を大学の入学基準としている限り、「英語を話せる日本人が増えることはないでしょう」とも書かれています。
もちろん、インターナショナルスクールについてどのような学校生活か書かれています。
しかし、本著で目から鱗が落ちるのは、白雲龍さんの日本の教育の分析です。
日本の教育についても分析し『学級崩壊』について原因をこう述べています。
『学級崩壊』の主原因は、日本の学校制度が、時代についていけなくなったことだと私は感じています。
(略)多様化に学校教育は答えることが出来ていません。(略)日本の学校教育は、西欧文明に追い付け追い越せということを目標としてきましたが、それが達成されたとき、目標を失ってしまいました。
しかも、情報化が進み、今までの学校が生徒にインプットしていたものは、先生に頼る必要が無くなってしまったのです。
この本が書かれた当時、今のようにTEDやハーバードなどの大学講義が無料でネット公開されるとは考えられませんでした。
しかし、10年以上前に、このような動きを指摘し、言い当てています。
さらに分析は続きます。
ところが教える側はそういったことを考えず、相変わらず情報をインプットだけするような画一的な教育を実践し続けてきました。
その結果として、生徒や社会の多様なニーズ、価値観等に対応できなくなったのです。
それでは授業がつまらないのも当然でしょう。
(略)日本の社会の中にあっては、まだまだ学歴信仰は根強く、卒業という資格のために多くの生徒は学校へ通います。
これが『学級崩壊』を招いているのだと思います。
では、インターではどのような教育がおこなわれ、なぜ『学級崩壊』が起こらないのか?
インターには、日本で言うところの『学級崩壊」というものはありません。
授業をエスケープする生徒はたまにいますが、授業に出席した生徒は集中しています。
その理由について日本の教育とインターの教育の違いから、分析しています。
これは授業が日本のように知識を単純に覚えるだけでなく、個々の体験などを通し、考えるなかで知識も修得していくというスタイルが圧倒的だからです。
インター(略)は、異文化が教室のなかで出会いますから、生徒にとって新鮮で魅力的です。
(略)当然のことながら、多様な価値観が存在しますから、どれが少数派でどれが多数派というなことが成立しません。
インターの本質へ迫ってきます。
そこではあらゆる異文化・価値観が尊重され、時には学習の対象となります。
その意味において、生徒は、学校(授業)への参加を望むのです。
そして、『学級崩壊』の考察から結論、解決法へ向かいます。
つまり『学級崩壊』を止めようと思ったら、生徒の多様な価値観・ニーズを満足させるような授業を展開しなければなりません。
最後は、学校教育制度の改革への提言でまとめられています。
(略)『学級崩壊』を止めるためには、多様な教育の場の創設、単位の互換性、教師個々の裁量権の拡大等々がなされなければならない(略)。
それは、教師、親、生徒の努力だけでは解決できるものではなく、現在の学校教育制度の根本的な改革が必要ではないかと思われます。(略)
本著では、インターの教育からさらに日本文化の分析へと続いています。
日本文化への分析も「なるほど!」ということが多く書かれています。
白雲龍さんの名言
私は息子が清泉インターの幼稚園に三歳で入園したとき、「髪の毛の黒い人にはお辞儀をしなさい。髪の毛の黒くない人には、握手してもよい」と教えました。
実生活で使える作法だと思います。
さらに、そこにはもう一段深い考えがありました。
これは、国際社会の中で西洋人とも、また、東洋人としても生き延びるための知恵として教えたつもりです。
(略)「お前はインターで学けれども、東洋人として生きていかなくてはならないんだよ」
このエピソードには、簡単そうで、深い話です。
今度は、学校帰りのエピソード。
ある日の学校の帰り、ジュースの缶を道端に捨てている中学生を注意しました。
その生徒は、放課後で学校外であると私に主張しました。
こう主張するところが、日本の学校の先生とインターの生徒との違いかもしれません。
(略)今さら言うべきことではないかもしれませんが、親の価値観、日ごろの態度、言葉、行動と家庭内の教育というのは、子どもの成長すべてに反映されています。
そして、これは、万国共通です。
親がともかく自分の生き方を子どもにみせる、これが躾けのスタートです。
子どもの価値観、態度、言葉などが外で出る。
そして、万国共通です。という言葉の裏に万国共通の大人の姿が見えます。
白さんの本著では日本のイジメについてさらに深く書いています。
白さんならではの鋭い切り口、多文化を踏まえた上での観察は重く、さらりと読める文章なのに、読んだ後にずっしりと残ります。
■こちらも参考にしたいですね。

インターナショナルスクールの「トリセツ」〜7分30秒で丸わかり〜
http://istimes.net/articles/805インターナショナルスクールとはどんな学校なのか?どのように学ぶのか?どのような生徒が通っているのか?また、どのような保護者が通わせているのか?などインターナショナルスクールについて取材を通してまとめました。乳幼児が通うプリスクールではなくインターナショナルスクールについてのまとめです。

なぜ、インターナショナルスクールは一年中、入学を受け入れるのか?
http://istimes.net/articles/838実は、多くのインターナショナルスクールでは一年中、生徒を募集しています。ただし、国内ではなく、海外からの転勤してくる家族を対象として一年中募集をしています。

インターナショナルスクールの先生になるには?これまでインターの教員採用は、知られていませんでした。しかし、グローバル教育に注目が集まるとともにインターの教育に興味を持つ方が増え、教員を目指す方も増えてきました。そこで、インターナショナルスクールの先生になる方法をまとめました。

インター受験の成功術〜プリスクールからどうやってインターに合格するか?
http://istimes.net/articles/845プリスクールからインターナショナルスクールを受験した場合、どのように対策を考えれ良いのでしょうか?意外と知られていないインター受験術。その方法と対策についてまとめました。インターナショナルスクールの小学部に進学したい、と考えたら一読してください。
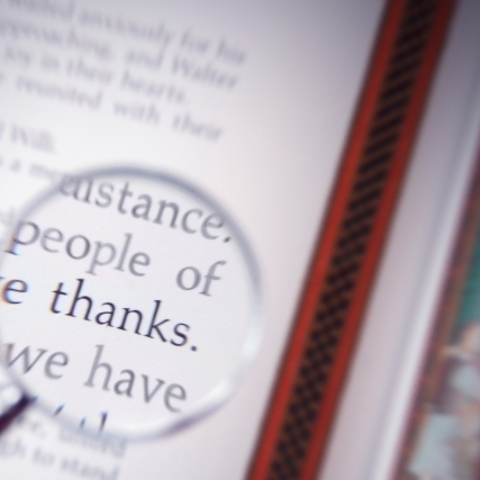







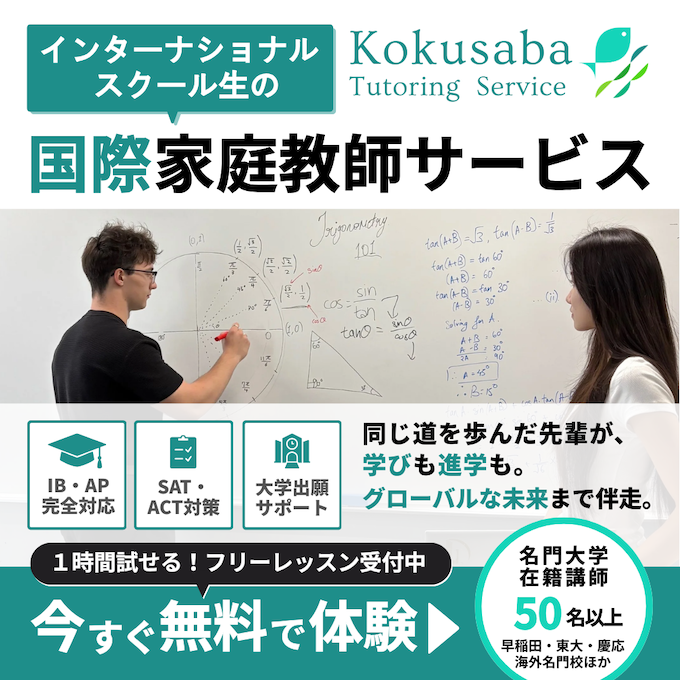























インターナショナルスクールタイムズの編集長として、執筆しながら国際教育評論家として、NHK、日本経済新聞やフジテレビ ホンマでっかTV、東洋経済、プレジデント、日本テレビ、TOKYO FMなど各メディアにコメント及びインタビューが掲載されています。
プリスクールの元経営者であり、都内の幼小中の教育課程のあるインターナショナルスクールの共同オーナーの一人です。
国際バカロレア候補校のインターナショナルスクールの共同オーナーのため国際バカロレアの教員向けPYPの研修を修了しています。