英語力があっても、インターナショナルスクール入学後の学校適応に苦労するケースもあります。
それが今回取り上げるケースです。
親として、言語の裏にあるコミュニケーションが日本の学校とインターナショナルスクールでは異なることを理解して、お子さんにアドバイスをしてみましょう。
「英語は得意だから大丈夫」——そう考えて、Kさん(小学4年生、仮名)は日本の公立小学校からインターナショナルスクールに転校しました。しかし、Kさんは、転校から3ヶ月を過ぎても学校に馴染めず、「学校に行きたくない」と言い始めてしまいました。
実は、インターナショナルスクールへの転校における最大の課題は、言語習得だけではありません。
言語の準備と同様に重要なのが、学校文化やコミュニケーションスタイルへの適応なのです。
見えない壁:日本の学校とインターナショナルスクールの文化的違い
インターナショナルスクールへの転校を考える保護者の多くが心配することは、学習言語が英語に変わるという言語的側面でしょう。
確かに語彙や読み書きの力は不可欠ですが、学校文化やコミュニケーションの期待値の違いに戸惑う子どもも少なくありません。

インターナショナルスクール文化を理解する3つの軸
3つの軸をもとに、日本の学校とインターナショナルスクールの文化的違いについて考えてみましょう。
軸1:集団調和 vs 個人の意見
日本の学校では、グループの調和を優先し、周りに合わせた行動をとることが良しとされ、個人の意見を強く主張することは好まれない傾向があります。
一方、インターナショナルスクールでは、個人の意見を尊重し、「自分らしさ」が評価されます。他の人と違う意見を持つこと、それを表現することが奨励されます。
軸2:察する文化 vs 伝える文化
日本の学校では、場の空気を読み、周囲と足並みを揃える態度が評価されます。非言語的なやりとりが多く、質問や自己主張が控えめになる傾向があります。
対照的に、インターナショナルスクールでは「伝える力」や「積極的な質問・意見表明」が重要視されます。自分の疑問や困りごとを言葉で明確に伝え、「I need your help」「I don’t understand」と言えることが大切です。ディスカッションやプレゼンテーションを通じて自分の考えを述べることも日常的に求められます。
軸3:正解を求める vs 探究する
日本の学校では、一つの正しい答えを導き出すことに重点が置かれ、先生の指示に従って学習を進めることが基本です。
また、確実な答えがわかってから発言する傾向があります。
一方、インターナショナルスクールでは、複数の視点から考える力や自ら問いを立てる主体性が重視されます。間違いは学びのプロセスの一部として受け入れられ、完璧でなくても自分の考えを表現する姿勢が評価されます。
冒頭のKさんは、授業では「自分から発言すること」「質問すること」が期待されていることに戸惑いました。休み時間には、日本の学校のように「グループの一員として自然に受け入れられる」のではなく、「自分から積極的に話しかけて友人関係を築く」ことが必要でした。
さらに、困ったときに「察してもらう」のではなく、「I need your help」と言葉で伝えることが求められました。日本の学校で「良い子」だった行動パターン、たとえば、「静かに座って指示を待つ」「周囲と同調した行動をとること」が、インターナショナルスクールでは「消極的」「自分の意見を表現できない」と受け取られてしまったのです。

転校前に家族ができる準備
インターナショナルスクールへの転校が決まった段階から、家族ができる準備がいくつかあります。
まず、転校先の学校文化を具体的に理解することです。見学や体験入学で学校の雰囲気を見て、授業の進め方を観察しましょう。
在校生や保護者の声を聞く機会があれば、教室外のコミュニケーション方法や放課後の活動の雰囲気も見えてきます。
そのうえで、「この学校では、自分の意見を言うことが大事なんだね」「わからないことは『I don't understand』って言っていいんだよ」など、日本の学校との違いを具体的に説明しておくことが有効です。
あわせて、教科学習で頻出する用語に親しんでおくことも、英語への学習言語の移行の助けとなります。
子どもの心の面を見守る姿勢は、準備段階からすでに始まります。不安や戸惑いの言葉を否定せず、「新しい環境に慣れるには時間がかかるよね」と受け止めることが大切です。インターナショナルスクールで新しい文化への適応に奮闘している子どもにとって、家庭は安心してリラックスできる大切な基地です。そうした環境を保つことを心がけましょう。
転校後しばらくは、「新しい環境に慣れること」を最優先にしましょう。宿題や課題が完璧にできなくても、過度に心配する必要はありません。
「友達ができたか」より「楽しい瞬間があったか」に注目しましょう。適応が進んできたら、「わからないところを一つだけ先生に質問してみよう」など、具体的な行動目標を立てながら、小さな成功体験を積み重ねていくことで、新しい学習環境への適応を支援していきましょう。
リソースの活用
学校の支援資源は積極的に活用しましょう。
英語が母語でない生徒のためのESL(English as a Second Language)やELL(English Language Learners)プログラムや、スクールカウンセラー、学習サポートの担当教員など、インターナショナルスクールには転校生の適応を支えるシステムが用意されています。
また、担任と、メールや面談を通じた定期的なコミュニケーションも欠かせません。日本の学校で慣れ親しんだ「先生にお任せします」という姿勢ではなく、「一緒に子どもをサポートするパートナー」としての関係構築が、インターナショナルスクールでは期待されています。
家庭での様子や子どもが使いやすい支援の方法を伝えると、学校側も教室での具体的な配慮につなげやすくなります。放課後のクラブ活動やイベントは、言語の負荷が比較的低く、共通の関心で関係を築ける場です。
友人関係づくりの入り口として大切にしたいところです。それでも不調が続く場合には、外部の専門家に早めに相談しましょう。
言語面でのつまずきが学習や自己表現に影響していると感じたら言語聴覚士へ、強い不安や睡眠の乱れ、気分の落ち込みが目立つなら臨床心理士やカウンセラーに相談することをお勧めします。早期の介入は、学校生活全体の負担を軽くし、子どもが新しい環境の中で本来の力を発揮するための近道になります。
見逃してはいけない「困っているサイン」
見逃してはいけないサインもあります。学校の話題を避ける、以前より言葉数が減る、表情が乏しくなるといった変化は、自分の思いや考えを言葉にできないストレスの表れかもしれません。
登校前に頭痛や腹痛を訴える日が増える、準備に時間がかかる、泣くといった行動も、心理的な負担のサインです。かつて楽しんでいた習い事や趣味への関心が薄れる場合、学校でのストレスが生活全体に波及している可能性があります。
サインに気づいたら、「大変なことがあるのかな?話してくれる?」と責めずに寄り添い、学校と状況を共有して連携を始めましょう。「しばらく様子を見る」は問題の長期化を招くことがあります。早めの相談が、子どもにとっても大人にとっても安心につながります。
まとめ

インターナショナルスクールへの転校は、言語習得だけでなく、文化適応のプロセスでもあります。
英語力の向上はもちろん重要ですが、同時に学校文化の違いを理解し、子どもの心理的適応を支えることが不可欠です。
インターナショナルスクールという多様性に満ちた環境での経験を通じて、子どもたちは一生の財産となる柔軟性とレジリエンスを獲得していきます。
異なる文化や価値観に触れ、それらを理解し、自分の視野に統合していく力は、グローバル社会を生きる上で何よりも重要なスキルとなるでしょう。
転校は決して簡単な道のりではありません。しかし、適切なサポートと理解があれば、子どもたちはこの経験を通じて大きく成長します。焦らず、子どものペースを尊重しながら、一歩ずつ、確かな歩みを積み重ねていきましょう。

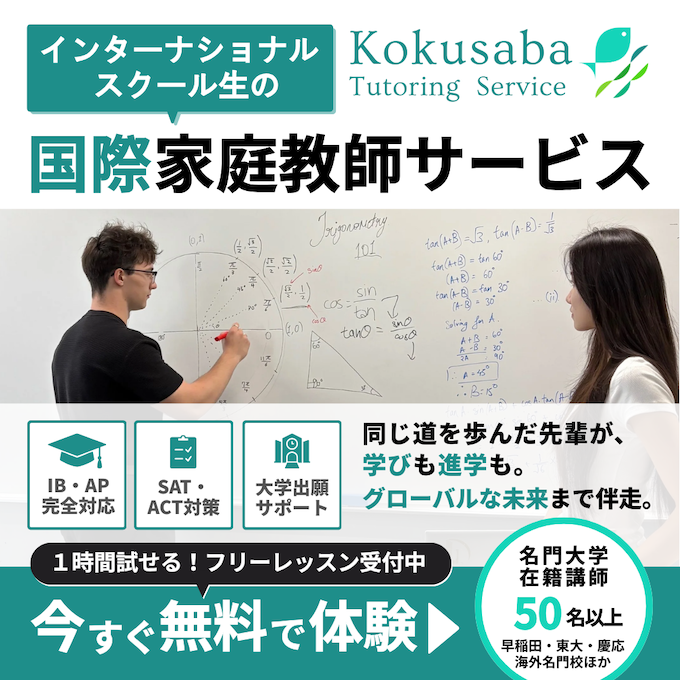




















25年以上の臨床経験を持つ小児専門の言語聴覚士。日米両国の資格を保持。2003年から2018年までの15年間をアメリカ・オレゴン州で過ごし、現在は神戸を拠点に「Suzuki Speech Therapy」を運営し、日本全国および海外の家族にオンライン・対面サービスを提供。構音障害、言語発達、ソーシャルコミュニケーションスキルを専門とし、特に多言語環境の子どもたちの異文化コミュニケーション課題のサポートを得意とする。現在、彩図社からバイリンガル育児に関する書籍出版を控えており、デジタル教材開発や多文化家族に関わる専門職・保護者向けの研修も実施。